「PROLO」は、子ども用自転車のヘルメットとロックの連動システムです。連日報道される交通事故の様子を目にし、子どもが命を落とす理由には、未解決の本質的な課題がまだ隠れているのではと考え、リサーチを始めた結果、「子供は、親の目の届かないところではヘルメットを外しがちである」「安全性を追求したヘルメットは多いが、そもそも被っていない」という気づきをもとに開発されました。
今回の受賞を受けて、チームリーダーの守屋氏は「大変光栄に思うと同時に、ここがゴールではないことを考えると、いっそう身が引きしまる思いです。受賞を糧に、技術や資金面でのハードルをクリアしていけるよう、積極的に関係者を募り、開発スピードを早めていきたいと考えています。」とコメントしています。受賞作品には賞金2,000ポンド(約27万円)が贈られます。受賞のニュースを受けて、法政大学デザイン工学部岩月正見教授は、「大学にとっても喜ばしいだけでなく、これから後に続く後輩たちに大きな勇気を与えることでしょう。」と話しています。
JDA国内審査員 緒方壽人氏は、「多数の応募作品の中には、発想は面白いが本当に必要なのか疑問であったり、解決すべき課題に取り組んでいるが本当に実現できるか判断が難しいといった作品も多い。その中で、今回の受賞作品はアイデアそのものの面白さ(WHAT)、なぜそれに取り組むのかという課題への着眼点(WHY)、それをどのように実現するのかという開発プロセス(HOW)、いずれの観点でも評価できる提案だった。」と総括しています。
国内準優秀賞は、下記2作品に贈られます。
Ubitone(ゆびとん)
盲ろう者のコミュニケーションをサポートするウェアラブルデバイス
遠隔のユーザーと身体的な動作の共有を可能にする、ウェアラブルなテレプレゼンスによる身体代理システム
< JDA2019 国内最優秀賞 PROLO>

概要:安全性を追求したヘルメットの開発は進んでいるが、そもそもの着用を促す製品は多くありません。親の目の届かないところでも、子どもに確実に着用してもらうため、「ヘルメットを自転車のロックにする」というシンプルなアイデアを仕組みに活かす。ヘルメットを着用するとロックが解除され、脱ぐとロックがかかる。ヘルメットには赤外線LEDとフォトトランジスタが取り付けてあり、照射した光を頭部が遮ることで、ヘルメットの装着を検出する。 作品動画はこちら
製作者:守屋輝一、児玉裕己、高見澤諒、中村友優、石黒雄大、上田雄翔、阿部俊介氏
法政大学大学院 デザイン工学研究科 システムデザイン専攻
JDA国内審査員 緒方壽人氏コメント:
「ヘルメットやシートベルトは、した方が安全な事は誰もが知っている知識だが、子どもに限らず現実の人間は根本的に面倒くさがりな性質を持っており、ユーザーの意識やモラルに頼るだけではなかなか徹底させることが難しい。この作品は、自転車のロックとヘルメットの着脱を連動させるというシンプルなアイデアだが、一連の自然な所作の中でヘルメットの着用を徹底させるという着眼点が素晴らしい。シェアサイクルや電動スクーターなど、今後、都市にパーソナルモビリティが普及していく中で安全性の確保が課題になるのは間違いなく、社会課題の解決という意味でも可能性を感じさせる。」
JDA国内審査員 川上典李子氏コメント:
「子どもたちの安全性のためにヘルメット着用率を上げたい」との発想に始まり、想定された使用者である子どもたちの心理面、本音もないがしろにすることなく、自発的に使用されるヘルメットのあり方が探究されている。ヘルメットと自転車のロックの連動においては既存技術を応用することで解決の道筋が立てられている点も興味深く、検証が重ねられた様子は動画を始め、応募内容から確かに伝わってきた。今後の計画における視点も明快であり、さらなる研究やフィールドテストを経たうえでの実現性の高さにおいても審査員の高い評価を得た提案である。」
<JDA2019 国内準優秀賞 Ubitone (ゆびとん)>

概要:盲ろう者は目が見えず、耳が聞こえないという二重のハンデによって大変な孤独にさらされている。自治体の支援のもと介助者のサポートを得ることができるが、特殊なコミュニケーションの習得を必要とするなどの課題があり、介助者の数は全国的に不足。Ubitoneは音声認識の結果を指点字という手法で盲ろう者の手に伝える。初期は卓上で使用する箱型のデバイスだったが、数多くのプロトタイプを通した使用者とのコミュニケーションの結果、現在は手首に装着する形状に至っている。作品動画はこちら
製作者:山蔦栄太郎氏 大阪大学大学院 工学研究科機械工学専攻
小西真広氏 大阪市立大学 電気情報工学科
JDA国内審査員 緒方壽人氏コメント:
「スマートフォンと指にはめる振動デバイスを組み合わせることで、視覚と聴覚の両方に障害を持つ盲ろう者のコミュニケーション方法のひとつである指点字をスマートに実現している。比較的低コストな技術の組み合わせでつくられており、専門知識を持たない健常者と盲ろう者のコミュニケーションの可能性を大いに広げる提案である。また実際に盲ろう者を対象にプロトタイプによるユーザーテストを繰り返しながら改良が重ねられている点も評価した。」
JDA国内審査員 八木啓太氏コメント:
「これまでの盲ろう者向けインタフェースと異なり、盲ろう者、健常者、ひいては、言語の異なる人々や、AIとのコミュニケーションも実現しうる、オープンで現代的なコミュニケーション手段の提案であり、グローバルなコミュニケーションインフラになりうるものである。汎用的かつシンプルな技術構成で社会実装性も高く、広く安価に提供できる点も含め、高く評価したい。」
<JDA 2019国内準優秀賞
Fusion: Full Body Surrogacy for Collaborative Communication>

概要: これまでの手法は、人工的な身体を通じた個人の経験の複製をすることに焦点が当てられていたが、Fusionは、遠隔のユーザーと身体的な動作の共有を可能にする、ウェアラブルなテレプレゼンスシステムによる身体代理(サロゲート)システムである。私たちの身体にテレプレゼンスロボットを結合することで視点を共有した共同作業を可能にする。オペレーターはサロゲートロボットを操縦し、視覚・聴覚・触覚フィードバックによってロボットにテレポートしている感覚を得、サロゲートロボットは着用者を同じ視点から支援し、身体的な共同作業を提供する。作品動画はこちら
製作者:ムハマド ヤメン サライジ (MHD Yamen Saraiji)氏 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科
佐々木智也氏 東京大学大学院 工学系研究科
JDA国内審査員 川上典李子氏コメント:
「視覚の共有に留まることなく、他者といかに”身体を共有できる”のか。3軸のヒューマノイドヘッドや軽量のロボットハンド等、継続的な研究の成果が反映された、現実的かつ洗練されたかたちのウェアラブルなテレプレゼンスロボット。身体的な経験の共有を始め、共同作業やインタラクション等の行為の支援に関しては、開発チームが理学療法やリハビリテーションでの使用の可能性を挙げている通りに、幅広い範囲の共同作業で機能しうるだろう。テレプレゼンスロボットの新たな可能性を示唆する意欲的な提案であり、今後の汎用性においても期待が高まる。」
JDA国内審査員 八木啓太氏コメント:
「テレプレゼンスロボットの中でも、共同作業やウェアラブルにフォーカスした本提案は、人類に新しい体験をもたらすものであり、そのアイデアを高いレベルで具現化している点も高く評価した。応用例は枚挙にいとまがないが、実社会にインパクトを与える今後の発展を期待したい。」
上記3作品を含む各国作品群は国際第2次審査に進みます。その中からTOP20作品が選ばれ、ダイソン創業者ジェームズ ダイソンによる国際最終審査に進みます。選考結果は、TOP20を10月17日に、最終結果を11月14日に発表予定。国際最優秀賞受賞者には、賞金30,000ポンドを、受賞者が在籍または卒業した教育機関に寄附金5,000ポンドが贈られます。
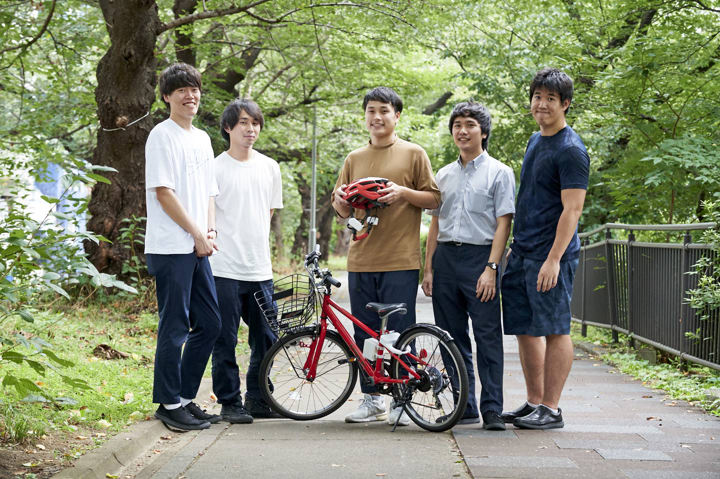


このページを次の場所で共有する